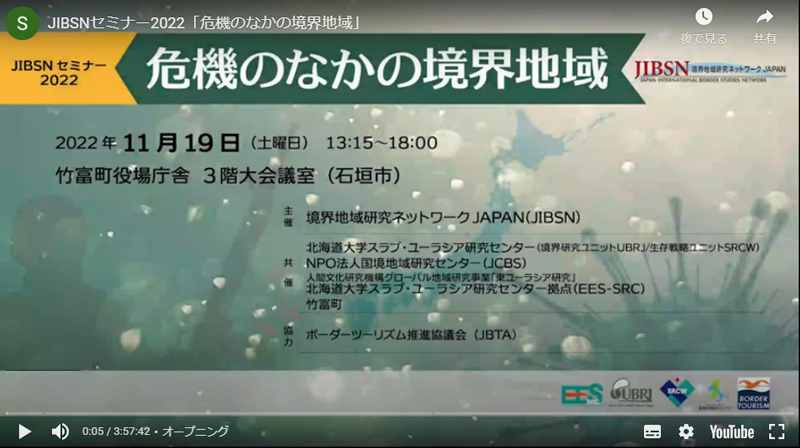私はANAグループで長く旅行業に従事していました。当然、成田空港や関西空港などで出国手続きをして搭乗し目的地まで行く行動を数え切れないほど経験しました。しかしながら飛行中に国境線を越えた、と言う意識などはなく、無事の帰国を安堵するのも入国手続きの時、つまり日本の地を踏んだ時でした。日本人の海外旅行はほぼ航空機利用なので当然ですよね。でも世界の海外旅行者約15億人(2019年)の内航空機利用は約54%と推計されています。世界では海路、陸路での越境がそれだけ多いと言うことですね。
日本は海に囲まれた島国であり世界で6番目に海岸線が長く、良港にも恵まれているにも関わらず海に引かれた国境線を越えて隣国へ行く定期航路は多くはありません。出港も寄港も豪華クルーズ船の話題だけに留まるところが消費額優先の今のツーリズムらしいとも言えます。
空路と航路を使ったハイブリッドな海外旅行
対馬空港は1500メートルですが、稚内にも五島福江、石垣島、与那国島にも2000メートル以上の滑走路を持つ空港があり、大都市との定期航空便があります。そこから少なくとも韓国、台湾と定期航路で繋がればハイブリッドな海外旅行が可能となり、その地域の若者たちを中心にプチ海外旅行の体験を提供できます。パスポートの所有者も増えるでしょう。また欧米からの東アジア3国の周遊の形も多様化します。でも日本の国境境界地域から定期航路でつながっているのは対馬と韓国釜山のみです。複雑な国際情勢という理由だけではなくLCCとの競争など経験的問題(儲からない)を理由として日本と周辺国·地域との定期航路はコロナ禍前から減り続けていますが、訪日需要が旺盛な台湾、韓国と日本の境界地域同士が繋がる意義は大変大きいと思いますが如何でしょうか。
大学生と話をすると海外旅行を体験してもらう取組みの重要性を強く感じています。行きたいけど行けないのではなく、日本国内の旅行で充分、海外旅行には興味がない若者が増えていると思います。従来の修学旅行ではなく大学生に海外を体験してもらう取組みに日本の国境境界地域から隣国へ渡るボーダーツーリズムを活用して欲しいものです。
様々なボーダー
ボーダーツーリズム(国境観光)が存在するのは国境が存在するからです。何を当たり前な事を言うのか、と思われると思います。歴史上の多くの争乱とその後の調停によって引かれたのが国境線であり、アフリカ大陸の真っすぐに引かれた国境線を地図で見ると人が引いたものだとわかります。そして国境線動くのです。国際情勢が可変であればナショナルボーダーも可変です。
一方でボーダーには自然や地形などの境界である地理的ボーダー(Geograhic boder)もあります。津軽海峡を通る動物相の分布境界線であるブラキストン線は有名です。また住民や産業などの境界線である社会的ボーダーもあるようで、ナショナルボーダーと違うことで悲劇が生まれもします。そして世界の分断された状況を見ると人間の心の中には心理的なボーダーも潜んでいるようにも思います。コロナ禍の時の日本では県境を越える、越えないが話題にもなり、地域観光事業支援(県民割)でも都道府県の境を改めて意識した方も多いでしょう。
国境境界地域での「こと体験」
光を観るが観光の語源とし、その光を磨くことが地域の活性化につながると言われます。その通りだとは思いますが、地域には光だけがあるわけではありません。陽光眩しい日本最西端の島・与那国島では台湾有事に備えた避難訓練が実施され住民は不安の中で暮らしています。ナショナルボーダーに位置することで防衛の砦の役割を担っている国境境界地域に観光は何ができるのでしょうか。
もっと日本の国境境界地域に目を向け、その独特の観光資源を経験し、海の向こうにある隣国との交流拠点として活用して欲しいと思います。旅や観光の価値は交流であり、交通手段を含み多様な交流を創造していくことが大事だと思います。国境線の向こうの国との交流は国境境界地域での「こと体験」だと思い、私は真に微力ながらボーダーツーリズムに取組んでいます。